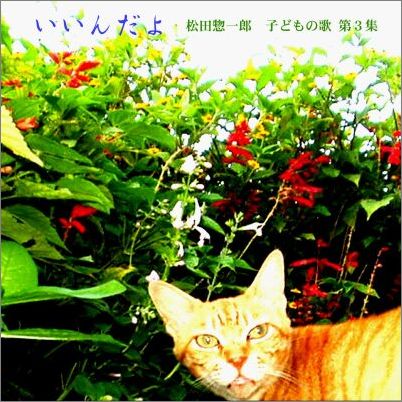松田惣一郎子どもの歌 第3集
「いいんだよ」
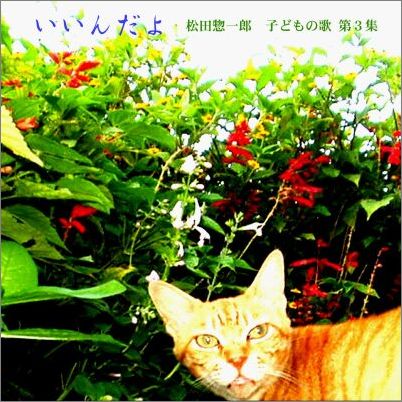
① 空は青空
② いいんだよ
③ 地球のそうじやさん
④ 夕ぐれになると
⑤ おしえてよ あおばずく
⑥ 空飛ぶにわとり
⑦ そのままでいいじゃない
⑧ はいたつまかせて
⑨ おふろに入って
⑩ 大きな木の歌
⑪ 空にはオリオン
⑫ どこかで会ったら
全作詞・作曲・編曲・プログラミング:松田惣一郎
2004年 8月 発表
「いいんだよ」ライナー・ノート
この作品集は、2001年から2004年の夏までに作った歌を収めたものである。
前作「ごめんね」を2001年に作ってから、いろいろなことがあった。
特に、音楽センター社の「クラスで歌う子どもの歌」に2曲採用されて全国発売されたことは、大きな刺激になった。
そして、毎年作ってきた運動会のダンス曲がそれぞれ親しまれたことも、創作の励みとなった。
そうやってできた12曲を、この作品集にまとめてみた。
それでは、それぞれの歌が生まれたいきさつなどを書いておこう。
空は青空
「2000・4・29 堤防上で詞曲同時に発想」とメモにある。まだ車の免許を持たずに自転車で走り回っていた頃、よく晴れた大淀川の河川敷で思い浮かんだ歌である。
それを2年後の春に作り直し、その年受け持った2年生に歌ってもらった。次のアルバムを作るなら1曲目にしようと、早くから決めていた歌だ。
いいんだよ
低学年の子どもはよく泣く。「泣かなくてもいいよ」という歌を作ろうと思ったが、逆じゃないかなと思えてきた。悲しかったら泣けばいいんだ。そう思いながら作った歌である。
負けて泣き、何かを失って泣き、子どもの一日はそんな繰り返しである。
地球のそうじやさん
2001年の運動会、高岡小3年生のダンス曲である。最初は「おふろに入って」みたいな軽い感じで着想した歌だが、だんだん作っていく内に世界が広がって、環境問題の歌になってしまった。
けっこうシビアな歌詞であるが、同学年で組んでいた米倉先生が、楽しく軽快な振りをつけてくださったので、明るいダンスに仕上がった。環境問題を扱ったダンス曲なんてそんなにないだろう。
夕ぐれになると
子どもの頃、兄はいつも縦笛を吹いていた。テレビも新聞もない貧しい家の、それは一種の遊びだった。するととうもろこし畑の向こうの家から、友人が吹き返す。こちらも負けずに吹き返す。
夕暮れに笛の音というと、加藤登紀子の「灰色の瞳」を思い出す人もいるだろうが、僕の頭にあったのはそんな幼い頃の風景である。
おしえてよ あおばずく
2003年の運動会、高岡小1年生のダンス曲である。はじめ、学校にやって来るアオバズクをもとに、やさしい子守唄を作っていたのだが、運動会のダンス曲に使うと決まったとたんに、こんなにぎやかな歌に変わってしまった。
「なんでだろう~」の動きを取り入れた同僚の村橋先生の振り付けで話題を呼び、2004年の全校ダンスでも踊られた。
空飛ぶにわとり
アオバズクの前の年、高岡小2年生が踊ったダンス曲である。狭い小屋に閉じ込められた鶏を見て思いついた歌だが、鳥インフルエンザが問題になった後だったら使えなかったかもしれない。
ダンスは、同僚の二見先生が、「ニワトリ・ウェーブ」などという奇抜なアイデアを考え出し、これまた愉快な踊りとなった。どういう偶然か、いつも組む先生がダンスの達人ばかりで助かっている。
そのままでいいじゃない
この歌は、曲だけが早くからできていたが、詞がなかなかできなかった。
公園の池を見ていて「そのままでいいじゃない~」というフレーズが浮かび、諫早湾干拓問題などに関心を持っていたので、環境問題を扱った歌を作ろうと思った。
ぼくはもちろんあらゆる開発を否定しているわけではない。でも、えげつない金儲けのために取り返しのつかないことが行われているのを見ると、「本当は自然はそのままが一番いいんだよ」と言いたくなる。
はいたつまかせて
1年生の国語の教材にある「ゆきのひのゆうびんやさん」を劇にした時に、簡単な歌を3つ作った。これはその内の1つ。
短時間で気軽に作った歌だったが、クラスの子ども達が歌ううちに自分でも気に入ってきた。
おふろにはいって
風呂洗いというのは、1年生でもやれて、けっこう貢献できるお手伝いの一つだ。これは、生活科の授業なんかでも使えるお手伝い奨励ソング。
大きな木の歌
2年生を教えていた時に、窓から校舎裏にある高い木が見えた。それを見て詞と曲が同時に浮かんだ。
思えば人間の寿命は短い。
空にはオリオン
全体に明るく元気な歌ばかりなので、最後に作って入れた曲。
我が子がまだ幼い頃暮らした南郷村は、星がきれいに見えた。村の道を、星座を教えながら歩いた記憶がある。クラスの子を夜運動場に集めて星の授業をしたこともあった。
今勤めている高岡小には、いろいろな事情で親と暮らせない子達もいる。何気ないような親子の時間が、ずっと心に残る思い出となることもあるだろう。
どこかで会ったら
2003年の3月、卒業シーズンにふとできた歌である。翌年の「6年生を送る会」で、1年生に歌わせようとしたら、難しすぎて歌えなかった。別れの歌にしてはちょっとテンポが速いが、中・高学年なら歌えると思う。
最後に、歌っている我が家の子ども達について紹介したい。二人の協力があるからぼくも家で作品を作ることができる。
6と11以外の全ての曲で歌っているのは娘の春佳。喉の調子が悪い上に本人の得意でない無理なキーを頼んだので、高い音はつらそうだったが、がんばってくれた。
息子の尚之も6,9,12で歌っている。受験生ながら協力してくれた。4,6と7から後は僕の声も入っているが、息子の声と似ているらしい。歌には自信がないが、11は署名のつもりで一人で歌った。
聞きづらい部分もあると思うが、もともと鑑賞用ではなく、いっしょに歌ってもらうためのものであるので、ご容赦願いたい。
後半はカラオケを収録したが、容量の関係で、11はカットした。
それから、高岡小の子ども達にもあらためてお礼を言いたい。この作品集は、高岡小の子ども達が歌ってくれたり、発想を与えてくれたりしてできたものばかりである。子ども達の歌声は、いつも最高のやる気を与えてくれる。
(2004・8・28 記)
|
 いいんだよ
いいんだよ